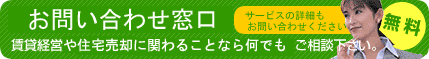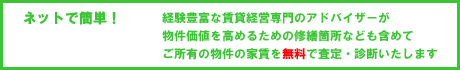
動機の錯誤(どうきのさくご)
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。
従って、動機そのものが思い違いに基づくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本来できないはずである。しかし実際にはこうした動機に関する思い違いが「錯誤」の問題として争われることが非常に多いため、判例ではこうした動機に関する思い違いも次の3つの要件を同時に満たすとき「錯誤」として取扱い、表意者の保護を図っている。
1:法律行為の要素の錯誤であること
法律行為の要素とは「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことである。このような重要な部分について、動機の思い違いがあれば、表意者を保護しようという趣旨である。
2:動機が明示または黙示に表示されたこと
動機が何らかの形で表示され、相手方がその動機を知ることができたことである。これにより相手方が不測の損害を受けることを回避しようとする趣旨である。
3:表意者に重大な過失がないこと
これは通常の錯誤と同じ要件である。表意者が少し注意すれば、要素に該当する動機の思い違いを回避できた場合には、その表意者は保護しないという意味である。