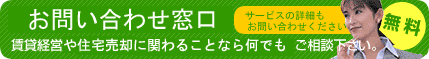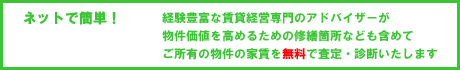
開発許可を与える基準(市街化調整区域における?)(かいはつきょかをあたえるきじゅん(しがいかちょうせいくいきにおける?))
知事や指定都市等の市長が、「市街化区域」等において開発行為を行なおうとする者に開発許可を与えるためには、その開発行為が都市計画法第33条の基準を満たしていることが必要である。
これに対して、知事や指定都市等の市長が市街化調整区域で行なわれる開発行為について開発許可を与えるためには、当該開発行為が、都市計画法第33条の基準に適合するだけでなく、都市計画法第34条に規定する基準にも適合するものであることが必要とされている。
この都市計画法第34条に規定する基準に適合する開発行為とは、具体的にはおおよそ次のようなものである。
1)周辺の地域の居住者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等をつくるための開発行為(都市計画法第34条第2号)
2)市街化調整区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物等をつくるための開発行為(都市計画法第34条第2号)
3)市街化調整区域内に存する観光資源の有効な利用上必要な建築物等をつくるための開発行為。具体的には宿泊施設など(都市計画法第34条第2号)
4)農林漁業生産物の加工等に必要な建築物等をつくるための開発行為(都市計画法第34条第4号)
5)市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であり、おおむね50以上の建築物が立ち並んでいる地域のうち、都道府県や指定都市等の条例で指定する土地の区域内において、当該条例により支障がないものとして認められた開発行為(都市計画法第34条第8号の3)
6)都道府県や指定都市等の条例で定められた一定の開発行為(都市計画法第34条第8号の4)
7)市街化調整区域に編入された日から6ヵ月以内に届け出た者が、5年以内に行なう開発行為(都市計画法第34条第9号)
8)開発行為を行なう区域の面積が20ha以上(都道府県の規則により5ha以上にまで引き下げ可能)の大規模な開発行為であって、計画的な市街化を図る上に支障がないと認められ、都道府県等の開発審査会が同意したもの(都市計画法第34条第10号イ)
9)開発行為を行なう区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為であって、かつ、市街化区域内において行なうことが困難または著しく不適当と認められ、都道府県等の開発審査会が同意したもの(都市計画法第34条第10号ロ)
なお9)は、具体的には、農家が分家をするための住宅、ガソリンスタンド、ドライブイン、市街化調整区域内の事業所の従業員のための住宅でやむをえないものなどを指している(都市計画法第34条第10号ロ、昭和44年12月4日建設省通達)