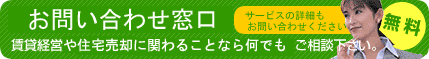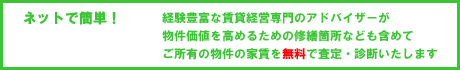
免許の基準(めんきょのきじゅん)
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項)。具体的には次のとおりである。
<なお下記5・6・11の「役員」の定義は役員(免許の基準における〜)を参照のこと>
1)免許申請書等で、重要な事項の虚偽記載等がある場合
宅地建物取引業を営もうとする者が提出した免許申請書や免許申請書の添付書類において、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項本文)。
2)専任の宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない者
宅地建物取引業を営もうとする者が、その事務所に関して宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項第9号)。
3)成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものであるときは、免許を与えることができない(法第5条第1項第1号)。
4)一定の事情で免許の取消しをされてから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、次のア・イ・ウの事情により免許を取消されてから5年を経過しない者であるときは、免許を与えることができない(法第5条第2号)。
ア:不正の手段により免許を受けたために、免許を取消された者(法第66条第1項第8号)
イ:業務停止処分に該当する行為<法第65条第2項の行為>を行ない、特に情状が重いために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
ウ:業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
5)免許の取消しをされた法人の役員であった者で、法人の免許の取消しから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営んでいた法人が、上記4)のア・イ・ウの事情により免許の取消しを受けた場合において、聴聞の公示の日(免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された日)の60日前以内にその法人の役員(注)であった者は、法人の免許の取消しから5年を経過しない場合には、個人として免許を受けることができない(法第5条第1項第2号)。(詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)
6)一定の時期に廃業・解散等した個人(または法人の役員)で、廃業の届出等から5年を経過しない者
これは免許取消し処分が下されることを回避するために、廃業・解散等してしまった場合を指している(法第5条第1項第2号の2、第2号の3)。(詳しくは免許の基準(廃業等)へ)
7)刑事罰の執行を終えてから5年を経過しない者等
免許を取得しようとする個人が、過去に一定の刑事罰を受けた経歴がある場合には、原則として刑の執行を終えてから5年間は、免許を受けることができない。(詳しくは免許の基準(刑事罰)へ)
8)免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者 (法第5条第1項第4号)
9)宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 (法第5条第1項第5号)
10)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記3)から9)のいずれかに該当するもの (法第5条第1項第6号)
未成年者は、婚姻をした場合(離婚後を含む)または営業の許可を受けた場合には、成年者と同一の能力を有することとなり、法定代理人の同意なくして有効に法律行為を行なうことが可能になる。しかし未婚かつ営業許可のない未成年者は法定代理人の同意を必要とする(詳しくは未成年者へ)。そこでこうした未成年者については法定代理人が上記3)から9)の欠格事由に該当しないことが要求されている。
11)法人が免許を取得しようとする場合に、その役員(注)のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
12)法人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
13)個人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに上記3)から9)までのいずれかに該当する者のあるもの (法第5条第1項第8号)
(注)上記5)・6)・11)における役員は、実質的な支配力を有する者を含む広い概念である。詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと。
- 免許の基準(廃業等) / 廃業等の届出 / 免許の基準(役員の連座) / 役員(免許の基準における〜) / 免許 / 免許の基準(刑事罰) /