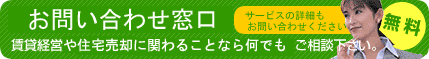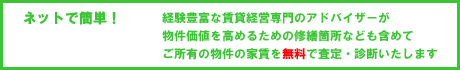
権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)
法人は法律の規定に従って設立される必要がある(民法第33条)が、法律の規定によらないで設立される非営利的な団体のことを「権利能力なき社団」と呼んでいる。
わが国の法制度では、法人は大きく分けて、次の3種に分類できる。
1)社団法人・財団法人(民法上の法人)
2)株式会社などの営利法人(商法等の法律による法人)
3)中小企業協同組合などの特別法にもとづく法人
それゆえ、例えば、同窓生の親睦という目的で法人を設立しようとしても、上記の1から3のいずれにも該当しないので、法人になることができなかったのである。
そのため、わが国には、法人となっていない非営利的な団体が無数に存在しているのが現状であり、こうした団体のことを「権利能力なき社団」と呼んでいるのである。
名前こそ「権利能力なき」となってはいるが、実際には法人と考えて良いような規模と資産を持っているケースも多数ある。
こうした「権利能力なき社団」は、銀行と取引し、不動産を購入・賃借するなどの活動を行う上で非常な不便を強いられているのが実情である。具体的には、権利能力なき社団は、所有する不動産を登記する場合には、代表者個人の名義の登記とするか、または総構成員の共有名義の登記にする必要がある。肩書付の代表者名義の登記は許されない(なお銀行預金については、肩書付の代表者名義の預金が認められている)。
なお、わが国では「特定非営利活動促進法」が98年12月に施行されたことにより、権利能力なき社団にも法人格を取得する道がようやく開かれたが、実際にこの法律により法人格を取得したケースはまだ少数にとどまっている。
その理由は「特定非営利活動促進法」はあくまで公衆のために便益を提供するような団体を対象にしているが、「権利能力なき社団」の圧倒的多数は、同窓会、互助会、町内会などの相互扶助目的の団体であるので、特定非営利活動促進法になじまないためであろうと考えられる。
このような実情を考慮して、法務省はつい最近になって、同窓会、互助会、町内会などに適した法人形態として、「中間法人制度」を創設した。この制度は平成14年4月1日から施行されている。